掲載日:2025年8月19日
糖尿病だけに起こるとは限りませんが、糖尿病があるとより進行しやすい大血管(太い血管)合併症として①壊疽、②脳梗塞、③虚血性心疾患があります。
壊疽『え』、脳梗塞『の』、虚血性心疾患『き』の頭文字をとって、『え、の、き』で覚えます。
(え)壊疽とは? ~足を失うリスクもある深刻な血流障害~
-

-
糖尿病患者さんの足に生じる感染、潰瘍または足組織の破壊性病変を糖尿病性足病変といいます。細小血管合併症である糖尿病性神経障害があると、靴擦れや熱傷などの外傷が出来やすくなってしまいます。下肢の閉塞性動脈硬化症も難治性潰瘍のリスクとなります。
糖尿病では免疫反応の低下が起き、こういった外傷などから感染が広がり、糖尿病性足壊疽(とうにょうびょうせいそくえそ)を引き起こしてしまうことがあります。
(の)脳梗塞とは? ~突然襲う、命に関わる脳の血管障害~
-

-
脳卒中は脳卒中、脳出血、くも膜下出血に分類されます。この中でも特に脳梗塞に関しては発症リスクを2~3倍高める独立したリスク因子ならびに発症後の予後不良予測因子として知られています。
アテローム血栓性梗塞とラクナ梗塞は特に糖尿病との関連が強いと知られており、発症予防には血糖値のコントロールが重要です。
(き)虚血性心疾患とは? ~心臓への負担と狭心症・心筋梗塞~
-
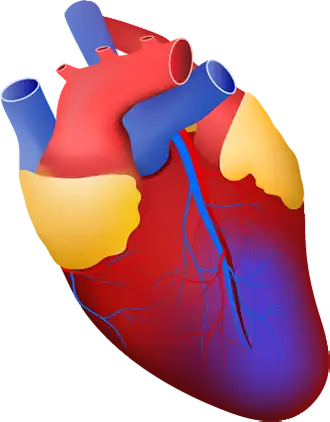
-
狭心症や急性心筋梗塞などを虚血性心疾患といいます。糖尿病による動脈硬化で心臓の血管が狭くなったり詰まったりすることで虚血性心疾患を起こすリスクが高まります。発症予防に血糖値のコントロールが重要です。
また、SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬といった薬は虚血性心疾患のリスクを低下させるというエビデンスが出てきているため、リスクの高い方や既往歴のある方には積極的に使用を検討します。
糖尿病以外にも注意が必要です!動脈硬化を促進する生活習慣病とは
糖尿病以外に動脈硬化のリスクを高める疾患としては、脂質異常症、高血圧症、喫煙、肥満、加齢などがあります。壊疽、脳梗塞、虚血性心疾患などの大血管症を予防するためには禁煙、減量をはじめ、コレステロールや血圧のコントロールも重要になってきます。コレステロールや血圧は糖尿病や喫煙の有無によって個別に目標値も変わってくるため、わからない場合は主治医に確認してください。
糖尿病性足病変を悪化させないためには普段から足をチェックし、傷ができていないか確認しましょう。また、足を清潔にし、ご自身に合った履物を選ぶ必要があります。足について気になることがありましたら、主治医や看護師にも普段の外来で聞いてみてください。
最近では血糖値を下げるだけでなく大血管合併症のリスクを減らすような内服薬、注射薬も出てきており、様々な論文でエビデンスが発表されています。内服薬や注射薬のことでわからないことがありましたらお気軽に相談ください。
【参考文献】糖尿病診療ガイドライン2024
- コラム「こんな症状がでたら糖尿病かもしれません」
- コラム「神経障害・網膜症・腎症 ~ 糖尿病の三大合併症「しめじ」について」
- 糖尿病・内分泌代謝内科のご案内
- 糖尿病・内分泌代謝内科医師によるコラムのご案内