掲載日:2025年1月15日
排尿時に刺すような強い痛みや眠れない程の頻尿、時には血尿でびっくりして私の外来を老若男女問わず患者さんが来院します。多くの場合、単純な細菌性膀胱炎のため抗生剤治療で治癒しますが、なかなか治癒に至らず、すぐに再発してしまうケースも見受けられます。
そこで今回は多くの方が直面する膀胱炎に関して詳しくみていこうと思います。
膀胱炎とは
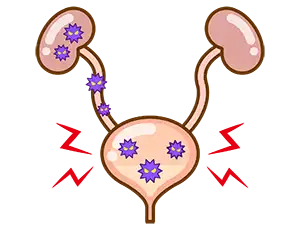
-
膀胱炎をはじめとする尿路感染症の原因は、尿道口から侵入した直腸常在菌による上行性感染、とガイドライン(※)で定義付けられています。膀胱炎は発熱を認めないことが特徴で、尿路の基礎疾患の有無により単純性と複雑性、臨床経過により急性と慢性に分類されます。
急性単純性膀胱炎
急性単純性膀胱炎は、尿路や全身に基礎疾患がない尿路感染症であり、強い膀胱刺激症状を認め、女性に好発しやすい疾患です。女性に好発しやすい理由は、①男性と比較し女性は尿道長が短いこと、②膣と肛門が尿道口に隣接しており、男性と比べ細菌が侵入しやすい環境が備わっていることに起因すると言われています。抗菌薬での速やかな改善が期待できる半面、再発する症例も見受けられます。
複雑性膀胱炎
複雑性膀胱炎は、尿路の基礎疾患(尿路の先天異常、神経因性膀胱、前立腺肥大症、膀胱結石、膀胱がんなど)や免疫系に障害を来す全身性疾患(糖尿病、ステロイド、抗癌薬投与中など)に合併した膀胱炎であり、誰にでも起こる可能性があります。また慢性の臨床経過をたどることが特徴です。
膀胱炎の症状・診断について
急性単純性膀胱炎の臨床症状は、頻尿・排尿時痛・尿混濁・膀胱部不快感などがあり、膀胱炎が進行すると肉眼的血尿を来すこともあります。基本的には発熱は伴わず、発熱を伴う時は腎盂腎炎などの合併を疑わなければなりません。短期間で再発する場合や、男性の場合は複雑性膀胱炎と考え、基礎疾患の検査を行う必要があります。
鑑別診断に挙がる他疾患
膀胱炎と同様の膀胱刺激症状を示す疾患として膀胱癌・膀胱結核・膀胱結石・過活動膀胱・間質性膀胱炎・出血性膀胱炎・放射線性膀胱炎などが挙げられます。
罹患率が最も高い膀胱炎の治療を終えてもなお膀胱刺激症状が長引く場合、また初診時でも排尿時痛のない肉眼的血尿などを認める場合は上記に挙げた疾患の可能性を探索した検査を行っていきます。
確定診断
膀胱炎に特徴的な臨床症状や臨床経過、および有意な膿尿(のうにょう)・細菌尿で確定診断します。尿沈渣(にょうちんさ)では、白血球数≧5/hpfを有意の膿尿と判定し、この膿尿と細菌尿の双方を認め、さらに膀胱刺激症状が見られる場合には膀胱炎として抗菌薬治療を開始します。近年耐性菌の増加を認めており、年齢や基礎疾患の背景・過去の培養結果をふまえ抗菌薬治療を開始しています。しかし最初に処方した抗菌薬が効果を示さない病原菌であるということも耐性菌の増加とともに増えてきてしまっています。そのため多くの場合、尿培養という検査を行っております。この検査では、病原菌にあった抗菌薬治療を適切に行えていたかどうかを次回再診日には確認することができ、再発予防に繋がるものと考えています。
管理・治療の目標
治療の目標は臨床症状および膿尿・細菌尿の消失であり、管理目標は再発・再燃の防止です。そのためには処方された抗菌薬を決められた日数分内服し、症状がなくなっても自己判断で内服を中断しないことが重要です。症状がなくなったからといってすぐに内服を中断してしまうと、病原菌の一部が残り、その病原菌が耐性菌へと変貌を遂げ、次回膀胱炎時には、前回効果があったはずの抗菌薬が効果を示さないということになってしまいます。
膀胱炎の予防としてできること
日常生活は、臨床症状がみられる間は適量の飲水を行い排尿量の増加に努め、寒冷やストレスなども増悪原因になるため、身体を冷やさないようにして十分な休養をとることが重要です。
- 膀胱内に菌を入れない
- 生理用ナプキンやおりものシートは3時間以内に変えて清潔な状態で保つ
- 排便後に「前から後ろ」へ拭くことで便の中にある大腸菌が尿道に付着する可能性を下げる
- 性行為後はすぐにトイレに行くこと
- 膀胱内で菌を増やさない
- トイレを我慢しないように心掛ける
- 水分を多めに摂る
- 身体の抵抗力を落とさない
- ストレスや過労・過激なダイエットを控える
- 下半身を冷やさない
- 栄養バランスの取れた食事摂取や睡眠時間の確保
無症候性細菌尿
臨床症状がなく慢性的に細菌尿が認められる無症候性細菌尿という状態の方が一定数いますが、その場合は抗菌薬の治療対象とはならず、頻尿や排尿時痛などの膀胱刺激症状を有する急性増悪時にのみ抗菌薬治療を行うことが耐性菌拡大の防止に繋がると言われています。ただし、妊婦の無症候性細菌尿については治療における妊娠中の有熱性尿路感染症を20~40%程度予防できるため、積極的な治療が推奨されており、抗菌薬投与を行っています。
再診
再診は抗菌薬の内服終了時期である3~7日後としており、臨床症状が改善しても治癒確認のために受診し、膿尿の消失と適切な抗菌薬治療がなされていたかを確認します。
治療開始から数日が経過しても臨床症状が改善しない、もしくは増悪した場合には抗菌薬の内服終了前でも相談して下さい。またアレルギー性皮疹・下痢症などの抗菌薬の副作用と思われる症状が認められた場合は速やかに抗菌薬の内服中止をお願いします。適切な内服状況にも関わらず膿尿が持続する場合には、尿培養と薬剤感受性検査結果に基づいて治療方針の変更を行い、それでも症状や尿所見の改善を認めない場合には「鑑別診断に挙がる他疾患」にある疾患や尿路の基礎疾患を念頭に置き精査していきます。
今回は多くの方が患う膀胱炎という疾患に焦点を当てて詳しく述べさせていただきました。今後の参考になれば幸いです。
【参考文献】(※)JAID/JSC感染症治療ガイドライン
- 泌尿器科のご案内
- 泌尿器科コラム「夜間のトイレの回数が増えた、これって異常?」